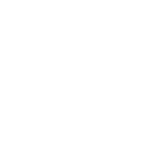洋服製造後に生じる寸法変化の要因と対策 〜素材特性と製造工程の観点から〜
衣類製造における品質管理において、**「寸法安定性」は製品の信頼性を左右する極めて重要な要素の一つです。特に、消費者使用後の洗濯や着用により発生する「縮み」「伸び」「ねじれ」などの寸法変化(Dimensional Change)**は、素材選定からパターン設計、縫製、最終仕上げまでの一連の製造工程に起因する複合的な現象です。
本稿では、アパレル製造・開発の現場で特に問題となる製造後の寸法変化がなぜ起こるのかについて、専門的視点からその原因と対策を解説します。

寸法変化とは何か?
寸法変化とは、衣類が製造直後の仕様寸法に対し、使用や洗濯を経ることで生地が物理的・化学的に変形し、寸法が変化する現象を指します。
JIS L 0217(洗濯試験方法)やJIS L 1096(織物・編物の試験方法)では、**収縮率(shrinkage)および寸法安定性(dimensional stability)**の測定が規定されており、製品企画段階における「許容範囲の設定」が求められます。
寸法変化の主な原因
1. 繊維素材の吸水収縮性・熱収縮性
素材の物性は寸法変化に直接影響を与えます。特に天然繊維(ウール、コットン、リネンなど)は吸湿性が高く、繊維内部に水分が侵入することで構造が変化しやすいため、洗濯・乾燥後に収縮が生じやすくなります。
- ウール:スケール構造により摩擦・水分・熱の影響でフェルト収縮(縮絨)が生じる
- コットン・リネン:水分を含んで繊維が膨潤 → 乾燥過程で収縮
- 化学繊維(PET、ナイロンなど):分子配列が安定しており、寸法変化は少ないが、熱可塑性の影響により乾燥条件で伸縮することもある
また、混紡素材では、繊維ごとの収縮率の差異によってねじれや歪みを誘発する場合もあり、混率バランスや撚糸構造の検討が重要となります。
2. 織編構造における応力残留と回復挙動
織物や編物は製造段階で経糸・緯糸(あるいは編目)に張力(テンション)がかかった状態で構成されます。このときに発生した残留応力は、製品が洗濯・加湿・熱処理されることで開放され、繊維が元のリラックス状態へと戻ろうとする「回復挙動」を引き起こします。
- 織物:経方向に収縮が大きく出やすい
- 編物:構造上の柔軟性により、伸縮性は高いが寸法安定性には注意が必要
寸法安定性を得るためには、生地段階でのスポンジング(縮絨・熱収縮処理)や、製品段階でのプレシュランク加工が有効です。
3. 洗濯・乾燥条件の物理的・熱的影響
家庭用洗濯機や乾燥機の使用による水分・熱・機械的負荷は、寸法変化の引き金となります。
- 温水洗濯:膨潤・熱収縮の促進
- タンブル乾燥:繊維の加熱・収縮、ねじれを誘発
- 遠心脱水時のねじれ応力:製品構造に偏りがあると、バイアス方向に寸法変化を起こす場合あり
JISでは「家庭洗濯試験(A法)」「業務用洗濯(F法)」などが規定されており、製品の最終使用状況を想定した洗濯耐久試験の実施が重要です。
4. 製品設計・縫製仕様による寸法変化誘発
寸法変化は素材・生地だけでなく、縫製仕様やパターン設計によっても誘発されます。
- 縫製糸のテンション過多 → 局所的な引きつり
- オフグレイン縫製 → 斜行・ねじれの原因
- パターン設計における縮率計算不足 → 想定外の縮み・つれ
縫製前の生地には、必要に応じた地の目修正や方向性の確認、部分的な防縮処理の適用が求められます。
寸法変化への対応策と製造現場での管理ポイント
◆ 素材選定と生地前処理の徹底
- 吸湿収縮性の高い素材には縮率データを基にした製品設計を行う
- スポンジング処理(蒸気収縮処理)やワッシャー加工により、事前に生地の応力を解消
- 織密度や撚糸方向のコントロールにより歪みを抑制
◆ 縫製工程におけるテンション管理
- 縫製ラインにてテンションバランスをモニタリング
- 伸縮素材では差動送り機構を適切に活用
- オフグレイン・バイアスによる斜行を防ぐための方向管理システムを導入
◆ 洗濯耐久試験によるフィードバック体制
- 製品化前における洗濯・乾燥シミュレーションの実施
- 特に肌着・スポーツウェアなど洗濯頻度が高い製品では、複数回洗濯後の寸法維持率の検証が必須
- 試験結果に応じた設計変更や縫製仕様の調整を行うフィードバックループ構築
おわりに:寸法変化は予測・制御可能な“設計要素”
寸法変化は偶発的な現象ではなく、素材物性・構造応力・加工条件の相互作用によって生じる**「予測可能な現象」**です。
つまり、製品企画・素材選定・設計・縫製・仕上げ・品質管理の各段階において、正確な知識と加工技術を持って対処することで、寸法安定性の高い製品を提供することは十分に可能です。
今後さらに高機能で繊細な素材が市場に登場する中で、「寸法変化」を制御することは、製品ブランドの信頼性・クレームリスクの低減・長期的な顧客満足につながる、不可欠な品質戦略の一環となるでしょう。